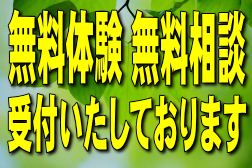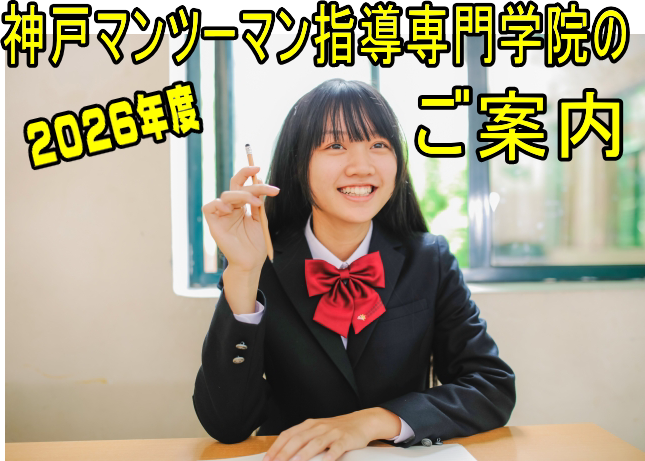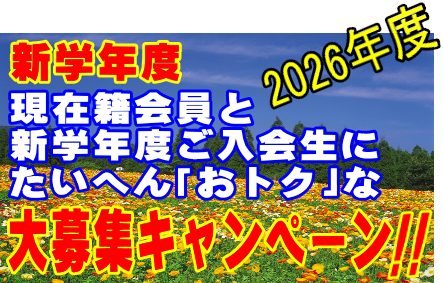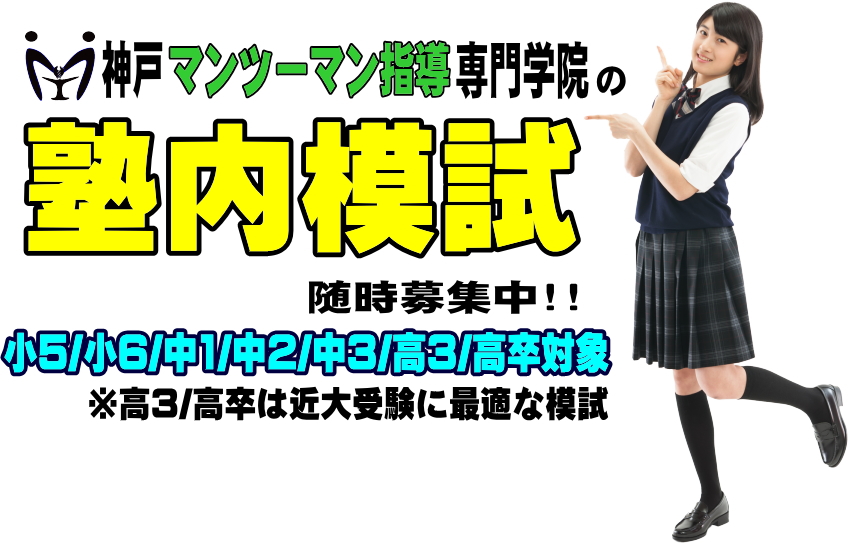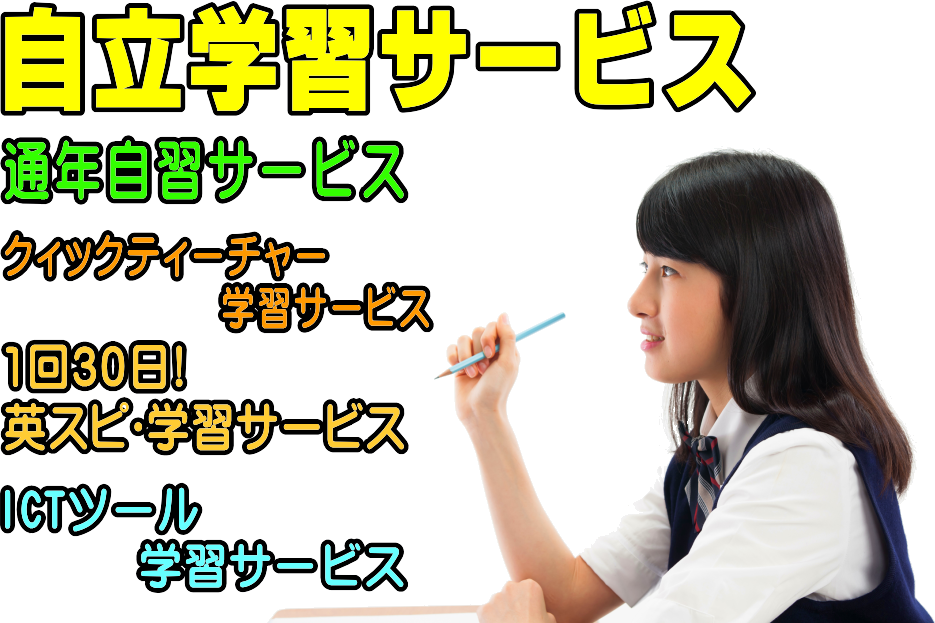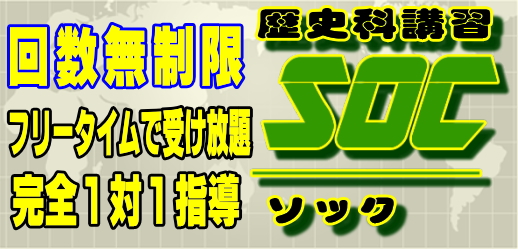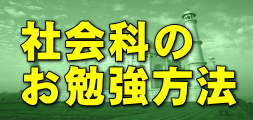自発的な学習を促す
マンツーマン個別指導、
家庭学習、
管理自習の特化型!!
〒652-0803 神戸市兵庫区大開通8丁目1番24西脇ビル2F
TEL 078-579-6225
営業時間:(月~金)午後4時~午後9時30分 土日・第5曜日休
社会科の成績を上げたい
目次
学院長が考える社会科について
当学院では、特に社会科の授業に力を入れております。
近年の国語力低下により、当然のことながら他の教科にも影響が出ます。ましてや社会科の扱う文章、絵、写真、グラフ、表といった素材を、国語科や英語科と同様、読む、聞く、話す、書くことが重要であり、日常生活にも関係する重要な教科であると位置づけております。このコンテンツでは、特に中学で学習する社会科を例に取り上げてご説明しましょう。特に際立ったものではなくごくごく当たり前ではあるものの、忘れがちな学習方法で、実践された子どもたちは確実に成績を上げております。
高校世界史の克服についてはこちら。
近年の国語力低下により、当然のことながら他の教科にも影響が出ます。ましてや社会科の扱う文章、絵、写真、グラフ、表といった素材を、国語科や英語科と同様、読む、聞く、話す、書くことが重要であり、日常生活にも関係する重要な教科であると位置づけております。このコンテンツでは、特に中学で学習する社会科を例に取り上げてご説明しましょう。特に際立ったものではなくごくごく当たり前ではあるものの、忘れがちな学習方法で、実践された子どもたちは確実に成績を上げております。
高校世界史の克服についてはこちら。
学習方法その1・教科書は、問題集よりも強し!
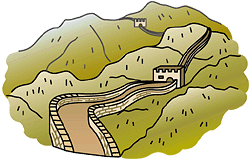 最近では、教科書がサブに回り、要点のつまったプリントや演習テキストをメインに授業を進める形態が増えておりますが、こうした素材はすべて教科書から取り出されたものであり、元の教科書を知らないで利用するととんでもないおぼえ方をしてしまいます。プリントやテキストが分からなくなったからといって、一問一答集や用語集だけをおぼえても、単体だけをおぼえても実践力が促せません。おぼえる前にまずは教科書を「見る」「読む」ことが大事です。とはいっても、文章の意味が分からなかったり、おぼえにくい言葉がゴロゴロして理解に苦しんだりすることでしょう。社会科のお勉強で最初に落ち込むところがココです。
最近では、教科書がサブに回り、要点のつまったプリントや演習テキストをメインに授業を進める形態が増えておりますが、こうした素材はすべて教科書から取り出されたものであり、元の教科書を知らないで利用するととんでもないおぼえ方をしてしまいます。プリントやテキストが分からなくなったからといって、一問一答集や用語集だけをおぼえても、単体だけをおぼえても実践力が促せません。おぼえる前にまずは教科書を「見る」「読む」ことが大事です。とはいっても、文章の意味が分からなかったり、おぼえにくい言葉がゴロゴロして理解に苦しんだりすることでしょう。社会科のお勉強で最初に落ち込むところがココです。しかし、最初はそれで当たり前です。「読む」だけでなく、「見る」ことも大事なのです。
それぞれのページを見ることで、"こんな地図があった!"、"こんな風景写真があった!"、"こんな絵があった!”、"こんなグラフがあった!"、"こんな人の写真があった"、"文章で太字で書かれたこんな言葉があった"といった印象からスタートして良いのです。何度も教科書をペラペラめくることによって、こうした印象がしっかりインプットされ、関心を引き起こすことからはじめるのです。実は教科書の絵や写真、グラフ、表などは、演習問題や入学試験問題などでけっこう使われており、"この写真が出たらこの言葉を答える"といった問題も多く出題されます。
たとえば歴史分野で、鎌倉時代に新しい仏教がたくさん出ました。教科書では、浄土宗、浄土真宗など各宗派と、法然、親鸞らのそれを開いた人たちの肖像画がズラリ1列に並んでいるページを必ず見かけることでしょう。地理分野でも、たとえば各気候帯での生活写真、北アメリカの農業や工業の分布を表す地図や、世界・日本問わず、各地方のページに登場する雨温図、公民分野では、裁判中での法廷の写真、三権分立の図、需要と供給のあの曲線グラフなど、文章を読まなくても必ず挿入される素材があり、これらの多くは問題として出題されます。
 そしてそうした素材が挿入されているページには、必ずそれらの説明が文章の中にあります。そこで「読む」作業、つまり"言葉を知る"作業に入ります。苦手な方は、説明の箇所が突き止められなくてうやむやにしてしまいがちです。『そのページに登場する「太字」のワードを含む文章、フレーズ』を突き止めましょう!当学院では、こうした突き止める箇所をしっかり伝えて、大事な部分を的確に指導します。教科書が読めない場合は、登場する言葉に対してもしっかり教えます。用語集や問題集を買うよりも、まずは"教科書"です。
そしてそうした素材が挿入されているページには、必ずそれらの説明が文章の中にあります。そこで「読む」作業、つまり"言葉を知る"作業に入ります。苦手な方は、説明の箇所が突き止められなくてうやむやにしてしまいがちです。『そのページに登場する「太字」のワードを含む文章、フレーズ』を突き止めましょう!当学院では、こうした突き止める箇所をしっかり伝えて、大事な部分を的確に指導します。教科書が読めない場合は、登場する言葉に対してもしっかり教えます。用語集や問題集を買うよりも、まずは"教科書"です。特に歴史分野では、古代から現代へと進んでいきますので、教科書を熟読した方はページの"厚み"で、どの時代かが把握できます。「この厚みの部分にはこんな写真やこんな絵やこんな太字の言葉があったな」と言えるまで活用できることを心がけて下さい。ちなみに中学生の地理分野では前半は世界、後半は日本に大きく分かれ、やや日本地理の量が多く載っております(特に地理は教科書に合わせて、地図帳も合わせ読むと、いっそう理解が深まります)。公民分野では、大きくは「現代社会」「憲法と政治」「経済」「国際社会」の4部門に分かれ、この順番で教科書に載っております。
学習方法その2・問題のパターンをいち早く知る!
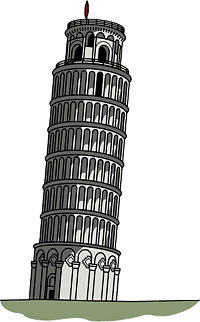 教科書がある程度使えるようになったら、ここで問題集の登場となるのですが、問題集は、やはり教科書に準拠したものを使うのが良いでしょう。こうした問題集には、教科書の重要部分(太字の言葉、絵、写真、グラフ、表など)を使った確認問題が必ずございます。この確認問題を最初は直接書き込まず、空いた用紙やノートなどで書いていきます。正答率が満足できたら(本当は正答率100%が良い)テキストに直接書き込んでいきます。特に当学院での授業や自習時では、社会科のみならず、テキストを直接書き込まず、ノートなどを用意してこれに書き込むことが重要であると教えており、先生に頼らず、家で一人学習して初めて直接書き込みを行うことで、自身がしっかり理解できたかを確認させます。これぞ復習です!
教科書がある程度使えるようになったら、ここで問題集の登場となるのですが、問題集は、やはり教科書に準拠したものを使うのが良いでしょう。こうした問題集には、教科書の重要部分(太字の言葉、絵、写真、グラフ、表など)を使った確認問題が必ずございます。この確認問題を最初は直接書き込まず、空いた用紙やノートなどで書いていきます。正答率が満足できたら(本当は正答率100%が良い)テキストに直接書き込んでいきます。特に当学院での授業や自習時では、社会科のみならず、テキストを直接書き込まず、ノートなどを用意してこれに書き込むことが重要であると教えており、先生に頼らず、家で一人学習して初めて直接書き込みを行うことで、自身がしっかり理解できたかを確認させます。これぞ復習です!確認問題でしっかり確認できたら、実践問題に移ります。問題は確認問題を除けば、決して文字だけで出題されることはありません。地理では地図、雨温図、地形図、統計表やグラフなど、歴史では年表、写真や絵、公民では表や図、時には写真などが必ず織り交ぜられます。
教科書を中心に問題が作られるので、「重要な部分がどういった形で出題されるか」は、パターン化されます。このパターンをいち早く知ることが大事です。
たとえば、地理では緯線と経線が引かれた世界地図では、「赤道はどの線か?」「本初子午線はどれか?」といった出題の確率は高く、時差を扱った問題も出やすいです。ヨーロッパ全土では、夏に乾燥する地中海性気候や、"偏西風"や"北大西洋海流"の影響によって高緯度ながら冷帯にならない西岸海洋性気候など、各地の気候を表す雨温図を答えさせる問題、また高緯度の北ヨーロッパでは"白夜"や"フィヨルド"を答えさせる問題などがパターンとしてからみます。「イタリア」「農業」とセットで問題文に出たら、「地中海式農業」「オリーブ」「ぶどう」「乾燥に強い」などを答えさせる問題パターンになるでしょう。他にもたとえば歴史分野では、"平清盛"といえば"太政大臣"、"承久の乱"といえば"後鳥羽上皇"や"六波羅探題"の問題が出題されるでしょうし、奈良時代で"●●した天皇は誰?"といえば、一般に中学で習う奈良時代の天皇は「聖武天皇」しか登場しません。公民分野では"地方自治"といえば直接請求権の内容を答えさせる問題があったり、"地方財政"といえば"地方交付税交付金"、"国庫支出金"、"地方債"などの言葉を答えさせる問題が出題される確率が高いです。
それぞれの問題にはそれぞれのキーワードがあるので、確認問題でおぼえた言葉をキーワードとしてどういう出題があるかを見ていく必要があるのです。"このキーワード"が問題に出てきたら、"このパターンで答えを要求してくる"のカラクリを見破っていきましょう。
学習方法その3・オリジナルのおぼえ方で!
 "何と(710年)大きな平城京"、"鳴くよ(794)ウグイス平安京"など、古来から有名なおぼえ方はありますが、人から教わったおぼえ方は忘れるものです。そこで、独自でおぼえ方を創作するのもおぼえる手段の一つです。たとえば、"(日本アルプスで)地図上で右からあいうえお順に「赤石」「木曽」「飛驒」"、"「日清戦争」、「日露戦争」、「第一次世界大戦」の勃発年は順に1894年、1904年、1914年と10年おき"、10年おきなら"1919年、1929年、1939年だとベルサイユ条約、世界恐慌、第二次世界大戦"、"真言宗は「空海」、「高野山」「金剛峯寺」で頭文字が「K」つながり(これ以外は最澄の天台宗関連)"、"「黄色の畑に長い稲」は中国の黄河流域の畑作と長江流域の稲作"などのおぼえ方を伝授しております。おぼえ方は他にもたくさんございます。
"何と(710年)大きな平城京"、"鳴くよ(794)ウグイス平安京"など、古来から有名なおぼえ方はありますが、人から教わったおぼえ方は忘れるものです。そこで、独自でおぼえ方を創作するのもおぼえる手段の一つです。たとえば、"(日本アルプスで)地図上で右からあいうえお順に「赤石」「木曽」「飛驒」"、"「日清戦争」、「日露戦争」、「第一次世界大戦」の勃発年は順に1894年、1904年、1914年と10年おき"、10年おきなら"1919年、1929年、1939年だとベルサイユ条約、世界恐慌、第二次世界大戦"、"真言宗は「空海」、「高野山」「金剛峯寺」で頭文字が「K」つながり(これ以外は最澄の天台宗関連)"、"「黄色の畑に長い稲」は中国の黄河流域の畑作と長江流域の稲作"などのおぼえ方を伝授しております。おぼえ方は他にもたくさんございます。高校で学習する世界史の克服とは!
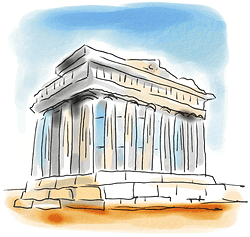 世界史の苦手理由として、"範囲が広い"、"名称が人か物か地名かわからない"、"時代が長すぎる"、"おぼえる用語が多すぎる"といった声をよく聞きます。名称の理解はとにかく、広範囲で、量が多いのは、他の科目も同じと言ってしまえばそれまでですので、あえて世界史を他の科目より面白くできるような説明をしてみようかと思います。
世界史の苦手理由として、"範囲が広い"、"名称が人か物か地名かわからない"、"時代が長すぎる"、"おぼえる用語が多すぎる"といった声をよく聞きます。名称の理解はとにかく、広範囲で、量が多いのは、他の科目も同じと言ってしまえばそれまでですので、あえて世界史を他の科目より面白くできるような説明をしてみようかと思います。
ナンシーやジョンソン、ヘンリーといった名前、どうみても英語です。中学の英語でも登場します。ということは、英語圏に存在する人物です。高校生で習得する英語の範囲であれば、世界史で登場するカタカナの中で、英語の言葉は見分けられると思います。
たとえばチャールズという名前は英語です。現代でもイギリス皇太子の名前で知られます。チャールズという語は、フランス語ではシャルル、ドイツ語ではカール、スペイン語ではカルロスになります。同じくヘンリーという英語名は、フランス語ではアンリ、ドイツ語ではハインリヒ、スペイン語ではエンリケと呼ばれます。またルイスという英語名は、フランス語ではルイ、ドイツ語ではルートヴィヒ、イタリア語ではルイージといいます。こうした登場するカタカナを見分けられるようにしていくことが重要です。
つまり、言葉の響きに慣れることで、どこの国に登場するかが分かっていくようになります。幸い世界史の教科書は国別に歴史が記述されるので、言語の響きをいち早く知ることが大事です。神聖ローマ帝国という国家が登場しますが、これをローマにあった国家と誤解する人がいますが、皇帝ハインリヒ4世や、カール4世といった名前が神聖ローマ帝国の皇帝として登場しますので、国家は現代のドイツにあるのではないかと推察して下さい。事実、神聖ローマ帝国とは現代のドイツにあった国家です(なぜ"ローマ"の名前がつくのかは、多少の説明がいるのですが)。
国単位でおぼえる範囲も確かに広いのですが、たとえば、~王国、~帝国と名のつく国家は中心人物はその国家の君主である王様や皇帝になります。古代エジプトでは"ファラオ"、ロシアでは"ツァーリ"です。イスラーム世界なら"カリフ"や"スルタン"、または"シャー"の肩書きのある方が君主となります(厳密に言えば説明が足りないのですが、高校世界史でのイスラーム世界はこうしておぼえて下さい)。彼らが時代の中心となって歴史をつくります。彼らが血統を絶やさず後継者を残すまで続きますが、世界史の見た場合、王様や皇帝といった君主のいる国家の、その血統ごとに時代を分けます。つまり世界史でいう時代は、中国やヨーロッパの各王国など君主のいる国家では、それぞれの時代を"王朝"として紹介します。たとえば、フランス王国のカペー朝、ヴァロワ朝、ブルボン朝など、インド・マガダ国のマウルヤ朝、グプタ朝など、中国の殷、周....清朝などです。血統が絶えると、その王朝は滅亡を意味し、王朝交代になります。ということで、各時代に活躍した君主を中心にまずは整理してみることです。建国者、統一者、全盛期、滅亡時といった時期に偉大な人物が登場するケースが多いです。
ちなみに、~王国の政治は王政、~帝国の政治は帝政、君主のいない国家は共和政がしかれるのが一般的です。
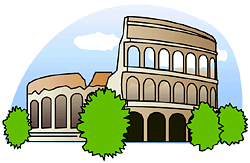 教科書も高校生用とはいえ、そう簡単に読み込めるものではありませんが、大学受験での世界史学習法で言われることは、まずは「教科書の精読」です。中学と同様、問題集を買うよりもまずは教科書を読むこと。
教科書も高校生用とはいえ、そう簡単に読み込めるものではありませんが、大学受験での世界史学習法で言われることは、まずは「教科書の精読」です。中学と同様、問題集を買うよりもまずは教科書を読むこと。読むのがキツければ"見る"ことからはじめましょう。文章に登場する地名は教科書の各章冒頭に添えられている地図に必ずあり、太字の言葉の説明は必ず注釈や挿絵、写真がそのページ内に添えられて分かりやすくしてくれています。
"見る"ことができたら、次のステージです。各ページでの「タテ」と「ヨコ」の流れを感じ取ってもらえたらと思います。各国の古代から現代にいたる「タテ」の流れと、それぞれの時代に他の国はどうなっていたかの「ヨコ」の流れをまずおおまかに(年代や年号を知らなくても何世紀ぐらいかを目処に)感じ取ります。
そして次のステージとして、各ページに登場する用語や人名を整理していくことで、教科書の内容も次第にわかりやすくなっていくことでしょう。
それでもイメージが沸かず、難しいととらえる場合もあります。そうなると用語集も必要となるのですが、世界史はロマンチックな科目ととらえますので、イメージをわかせるツールとして、用語集、資料集、地図帳などもいずれ必携アイテムとなるでしょう。ネットで検索して人物の肖像画や、文化史に登場する作品名などを目で見ることも大事です。YouTubeや画像検索で自分の目でとらえる作業も何かと必要になります。
そして問題演習です。
「私大入試では主に知識を振り絞って答え、
共通テストでは主に知識をヒントにタテヨコの流れを確認しながら答える。」
特に後者は憶えた知識をヒントに、思考力をふりしぼって状態や状況を表した文章を選ぶという傾向です。兵庫県公立高校入試の社会科は後者に近い出題形式も散見します。志望する学校の過去問がどんな形式で出題されているかをしっかり見極める必要があります。
さて、世界史に登場する人物は当然、その国では偉大な功績を残しました(中には時と場合により汚名を残した人物もいますが)。現代でもその栄光が讃えられております。世界史は世界の昔話ですので、これまで登場した各国の偉人達が何をして、何を作って有名になったかを知ってくれると世界史に対する興味も膨らむと思います。
最後に、これは個人的関心となりますが、世界史の学習ではこんな妄想も興味本位として使われます。たとえば、
- スペインがメキシコを征服しなかったら、今のメキシコでは何語がメインで話されているのだろうか?
- コロンブスが大西洋を西へ横断せず、アフリカ大陸を南へ下っていたら、アメリカ大陸はいつ発見されたであろうか?
- 玄奘がインドに行かなかったら、『西遊記』はつくられたであろうか?
- ワットが蒸気機関を発明していなかったら、蒸気機関車は登場したであろうか?
- アテネがペルシャ戦争に大敗していたら、ペリクレスの民主政治はおこったであろうか?
- 732年のトゥール=ポワティエ間の戦いでウマイヤ朝がフランク王国を打ち負かしていたら、西ヨーロッパ中にイスラム教が浸透したであろうか?
- フランス国王シャルル7世がジャンヌ=ダルクをイギリスに明け渡すことなく助けていれば、彼女は何歳まで生きたであろうか?
- ジャンヌをイギリスに明け渡さなかったら、シャルル7世の評価が変わったであろうか?
とはいえ、令和7年度の共通テストでは、旧世界史Bを改めた『世界史探究』単独での受験はなく、旧世界史Aと旧日本史Aが組み合わさった『歴史総合』とワンセットの選択です。日本の近現代史も項目に入ってきますので、単純に暗記するだけでは到底上手くいかず、よりタテヨコの背景や因果関係を徹底学習しないといけません。社会科は暗記科目で片付けられない意図がこの選択方法でもわかります。
当学院では、歴史科学習に特化した講習も行っております(中3~高3・高卒。中2以下は応相談)。学院長も講師として中学と高校の社会を指導担当しております(専門は世界史ですが、日本史、中学歴史を中心に教えています)。学院長が自ら指導する完全1対1のマンツーマン指導のコースもございます。ご希望の際はこちらをご参照下さい。